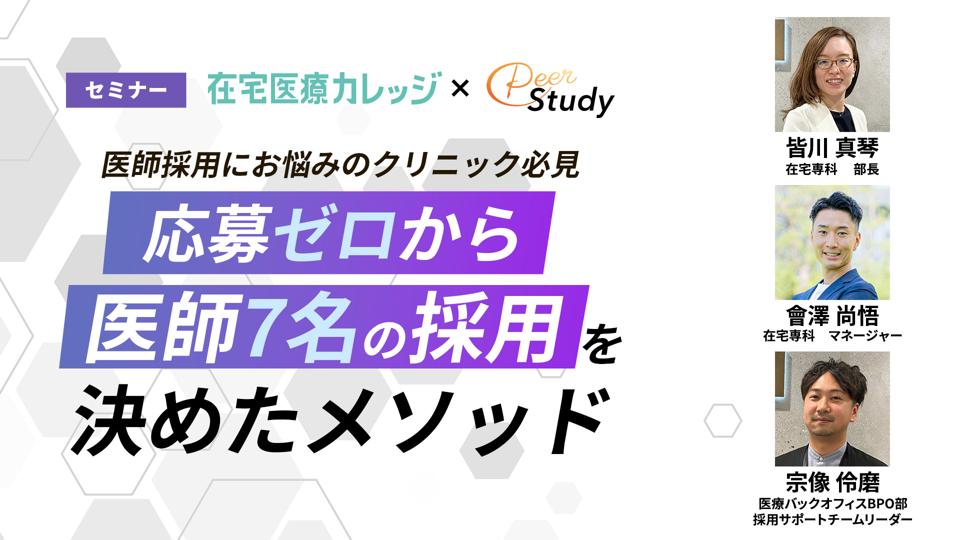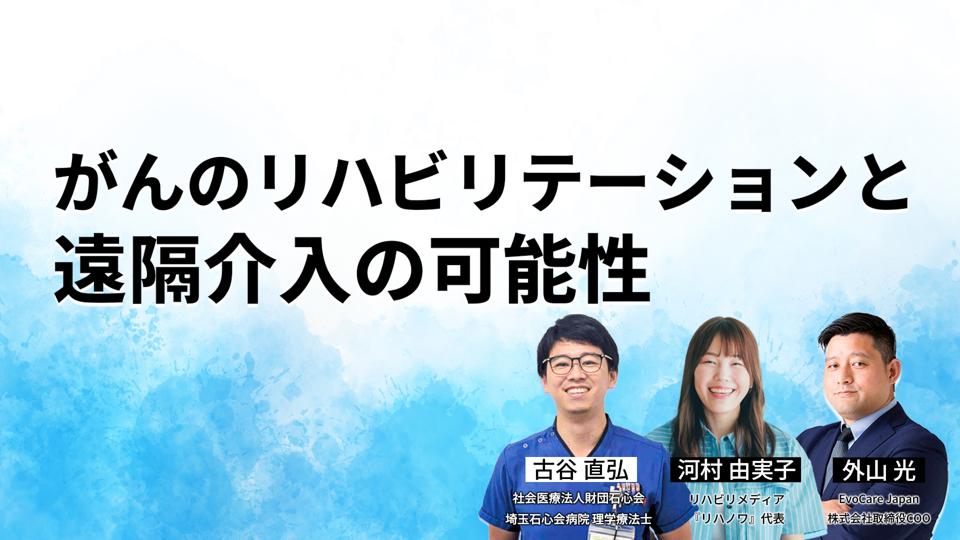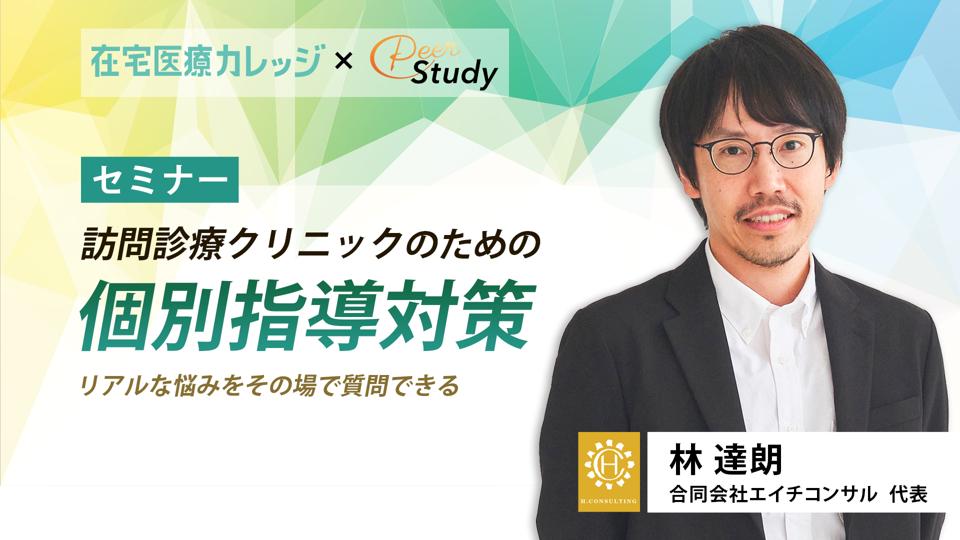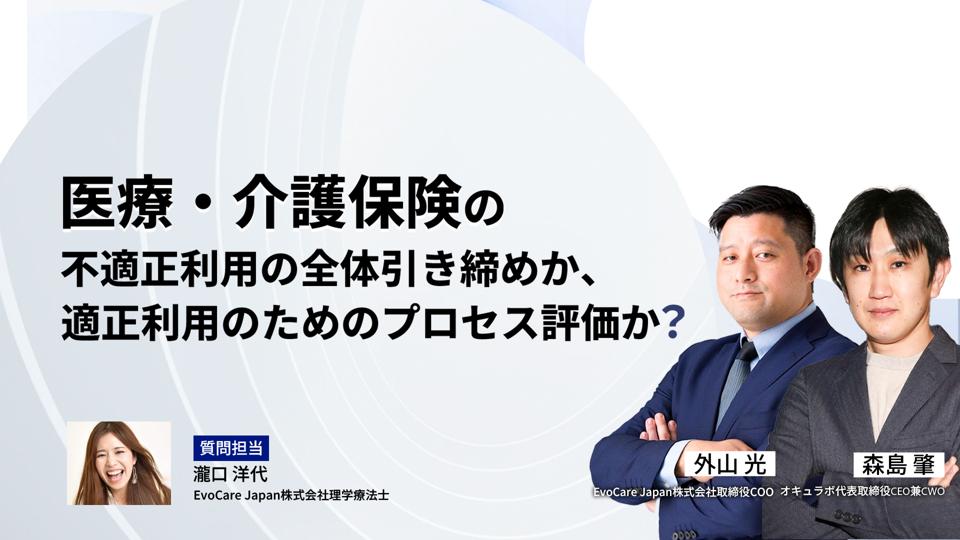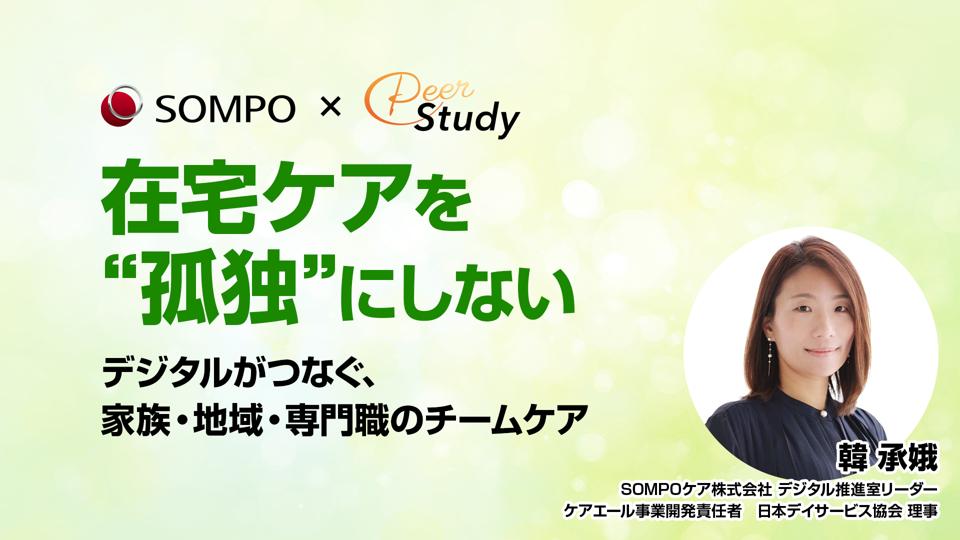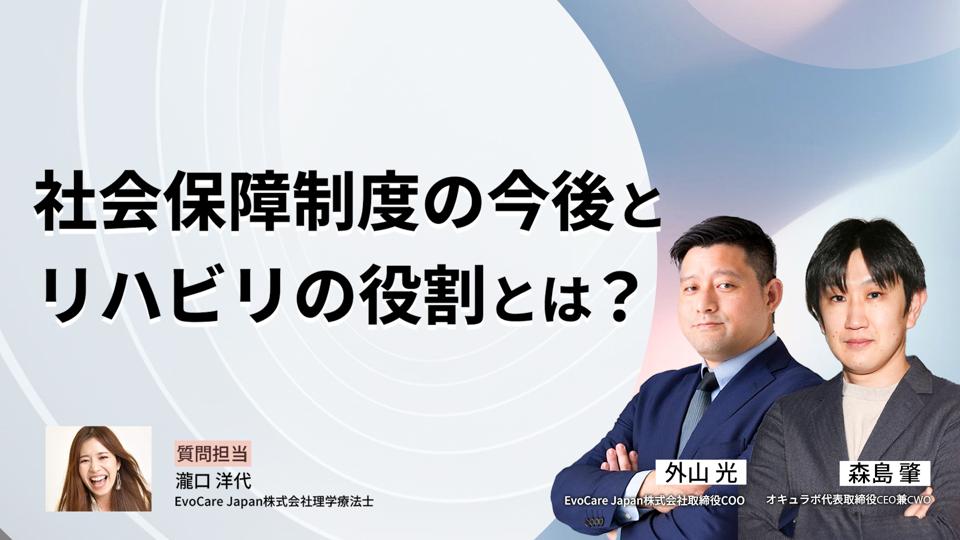中国北京の医療介護・認知症ケア最前線 北京視察ツアー2025 報告会
中国北京の医療介護・認知症ケア最前線
北京視察ツアー2025 報告会
北京で見た介護の現場は、
予想を裏切る連続だった…
認知症ケア、地域共生、死生観、テクノロジー…
日本の未来に通じる“気づき”を共有する専門職向け報告会。
■SPEAKER
■佐々木 淳 氏
医療法人社団悠翔会・理事長・医師
筑波大学医学専門学群を卒業後、三井記念病院内科・消化器内科、東京大学医学部附属病院消化器内科等を経て、2006年に当時まだ数少なかった24時間対応の在宅総合診療を行う診療所を開設。
以来、在宅医療をリードする存在となる。
2008年に医療法人社団悠翔会として法人化し現職。
現在、首都圏ならびに愛知県(知多半島)、鹿児島県(与論島)、沖縄県(南風原町・石垣島)に全25拠点を展開。内閣府規制改革推進会議専門委員(医療・介護・感染対応)。
主な著書
医学書院:『在宅医療カレッジ 地域共生社会を支える多職種の学び21講』
池田書店:『現場で役立つよくわかる訪問看護 アセスメントとケアに自信がつく!』
飛鳥新社:『在宅医療のエキスパートが教える 年をとったら食べなさい』
日本医療企画:『Re:CAREポストコロナ時代の新たなケアのカタチ』
■加藤 忠相 氏
株式会社あおいけあ 代表取締役・介護職
東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業後、神奈川県内の特別養護老人ホームに勤務。25歳の平成13年、株式会社あおいけあを設立し、グループホーム結、デイサービスいどばたの運営を始める。平成19年からは“小規模多機能型居宅介護おたがいさん”の運営を開始し、平成24年には『かながわ福祉サービス大賞?福祉の未来を開く先進事例発表会?』において大賞を受賞。“あおいけあ”をモデルとした映画『ケアニン?あなたでよかった?』『僕とケアニンとおばあちゃんたちと。』等の映画化にも携わる。NHK『プロフェッショナル?仕事の流儀?』等、数多くのメディア出演も果たす。平成31年2月には、Ageing Asia Global Ageing Influencer 2019(アジア太平洋地域の高齢化に影響を与えている最も影響力のある指導者)に選ばれた。
■細見 真司 氏
アイシーパートナーズ合同会社 代表執行役
医療法人のマネジメントを経て、2006年新生銀行に入行し、日本の銀行として初の有料老人ホームの不動産流動化を行ない、2010年にヘルスケアファイナンス部を創設する。
2014年よりデロイトトーマツにて、医療・介護セクターのM&Aアドバイザリー、及びアジア進出支援として、上海にて中国の投資家向けセミナー、台湾での新規事業進出支援等を行なう。2016年に厚生労働省「介護サービス事業者等の海外進出の促進に関する調査研究事業」の委員に就任。
2021年から霞ヶ関キャピタルにてヘルスケア事業推進部長としてホスピス住宅の開発投資を推進。2023よりグローム・ホールディングスの執行役員を経て、現在に至る。
■大西 真二 氏
合同会社 春岳(しゅんがく)代表
1969年生まれ。地元 三重県の高校を卒業後、車部品の製造会社へ就職。34歳の時に介護の世界へ転身。2010年・41歳になる歳に起業し古民家型小規模デイサービスをオープン。その後、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、サービス付き高齢者向け住宅をオープンし、2023年サービス付き高齢者向け住宅新館をオープン。普段はケアマネージャーとして従事している。
■小池 昭雅 氏
アイ・ウィッシュ株式会社 代表取締役/介護福祉士・介護講演家
介護福祉士としての経験を活かし、介護講演家として幅広く活動している。
群馬県高崎市に拠点を置き、アイ・ウィッシュ株式会社の代表取締役として、小規模多機能型居宅介護、デイサービス『オリジン』で在宅介護サービスを展開し、地域づくりや高齢者支援に対する強い情熱を持ち、介護業界の課題解決に向けて積極的に取り組んでいる。
講演や研修、介護事業所のアドバイザーとしても活動し、介護福祉の魅力発信や介護従事者のスキル向上を支援している。
■小田 直樹 氏
株式会社ブイキューブ 営業本部 副本部長
2008年ブイキューブ入社。岩手県出身。サービス業、製造業、情報通信業、公共など広範囲に渡り、各産業へ黎明期であったウェブ会議やウェブセミナーを活用したコミュニケーションDXの提案およびオンボーディングに携わる。
2020年よりマーケティング部門の副本部長を兼任し、マーケティングおよびセールス領域の全般を管掌。現在は、営業本部 副本部長としてエンタープライズDX事業およびサードプレイスDX事業の営業統括管掌。2024年9月よりオンライン診療ソリューションの事業責任者も兼任し、2025年5月オンライン診療/服薬指導ブース「テレキューブクリニック」をリリース。市場拡大を推進中。
■宮地 紘樹 氏
医療法人社団綾和会 掛川東病院 院長
10年間の外科医としての経験を経て、2014年から訪問診療に従事し、地域医療の枠を超えた新たな活動に尽力。2019年から静岡と東京の2拠点生活を開始し、掛川東病院院長として、地域初の24時間訪問診療や地域包括ケア病棟の立ち上げを推進。従来の医療機関が行成し得なかった行政、企業、住民を巻き込んだ地域活動にも積極的に取り組み、医療を中心に据えたコミュニティ形成を進める。地域住民同士が支え合う文化を醸成し、社会保障に依存しない持続可能な健康促進モデルの実現に邁進する。
■片山 紀子 氏
東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻死生学応用倫理専門分野 博士課程/保健師/看護師
済生会横浜市東部病院 働き方改革推進室
看護・介護系出版社や日本看護協会広報部等での勤務を経て看護職に転身。2015年より済生会横浜市東部病院こころのケアセンターおよびICUに勤務。2019年、厚生労働省医政局看護課に出向。2022年、出向元に復帰し非常勤で職場環境改善に取り組む傍ら、東京大学大学院人文社会系研究科に新設された死生学応用倫理研究室の博士課程に進学。臨床、行政、研究を往還しながら、死生観やケア、医療倫理に関する探究を続けている。今秋より、オックスフォード大学に留学予定。
■王 青 氏
日中福祉プランニング代表
中国上海市出身。語学学習を経て大阪市立大学経済学部卒業。アジア太平洋トレードセンター(ATC)入社。 大阪市、朝日新聞、ATCの3社で設立した福祉関係の常設展示場「高齢者総合生活提案館 ATCエイジレスセンター」に所属し、広く“福祉”に関わる。その後フリー。上海市民政局や障がい者連合会をはじめ、政府機関や民間企業に幅広く人脈を持つ。日本と中国の介護福祉分野を中心に、市場調査、マスコミ取材、ビジネス支援のコンサルなど多くの案件を手がけ実現し活動中。多数のメィデアに中国の高齢者問題を中心に執筆。
<進行・司会>
■志摩 宙人 氏
株式会社SHIMAMON DESIGN 代表/YOKOHAMA訪問看護ステーション 運営者/横浜市多業種交流会『浜CHAN』 会長
奥羽大学歯学部歯学科を卒業後、2013年7月より株式会社ウェルフューチャーに入社。
デイサービスや有料老人ホームにおいて管理者・施設長を務め、その後エリアマネージャーとして幅広い施設運営に携わる。
2019年11月からは株式会社ツクイにて本社営業部に所属し、介護業界のさらなる発展に貢献。
2023年6月20日には株式会社SHIMAMON DESIGNを設立し、2024年3月1日には「YOKOHAMA訪問看護ステーション」を開所。
医療・介護・デザイン・コンサルティングを通じ、柔軟な発想と幅広いネットワークを活かした事業展開を行っている。
また、多業種が交流する横浜市のビジネスネットワーク「浜CHAN」の会長を務めるほか、認知症の人と地域をつなぐ「RUN伴」において、YOKOHAMAや厚木・海老名・伊勢原 with 愛川・清川、相模原(デザイン協力)、山形(2024年デザイン依頼)など、各地域で活動を支援。
さらに、相模原市みらい交流会の役員としても地域社会の発展に尽力している。
医療・介護・デザインの領域を横断しながら、全国に広がるつながりを活かし、新たな価値の創造に挑戦し続けている」